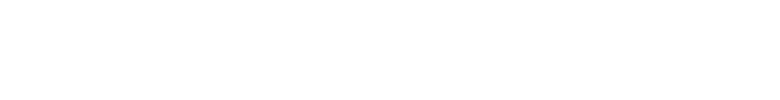フロントラインとは、最前線という意味。
2020年2月、豪華客船ダイヤモンドプリンセス号が横浜に入港した時のことを、覚えているだろうか。
全世界を巻き込んだ、ウイルスとの3年以上にわたる長い戦い。
日本では、横浜から始まった。
ウイルスの正体も治療法も分からない。
だが船内では、発熱して苦しむ患者が増え続ける。
考えたり、協議したり、準備したりする時間はない。
今すぐ、誰かが、対応しなければならなかった。
【フロントライン】のあらすじ
これは実話に基づき、未知のウイルスに最前線で立ち向かった人々の戦いを、オリジナル脚本で描いたドラマだ。
もちろん、みんな知っている。
ダイヤモンドプリンセス号から、あの騒動が始まったことを。
だがあの時、船内で本当はなにが起っていたのか、現場にいる人たちはなにをしていたのか、どんな葛藤や混乱があったのかは、よく知らない。
メディアやネットの情報に、世間は振り回された感がある。
【フロントライン】では、携わった医療関係者、厚生労働省職員、乗客、船のクルー、受け入れ先病院の人々、医療関係者を現場に送り出す家族、マスコミの立場から、あの出来事を描いている。
2020年2月3日、横浜港に入港したダイヤモンドプリンセス号の船内には、100人以上の発熱患者がいた。
香港で下船した乗客のコロナウイルス陽性が確認されたことから、集団感染が疑われる。
だが日本には、大規模な感染症に対応する専門機関はなく、災害時の医療ボランティア的組織DMATが派遣されることとなった。
感染症対策は専門外だったが、他に手を挙げる人も組織もない。感染症学会ですら、断ってくる。
誰もいない、でも誰かがやらなければ。
DMATの医師・結城(小栗旬)は、厚生省の役人・立松(松坂桃李)とともに地上で指揮を執り、医師の仙道(窪塚洋介)、真田(池松壮亮)らは看護師たちと乗船して、救護活動にあたる。
わざわざセンセーショナルに煽って報道するマスコミ、自分の意見が通らなかったことに立腹し、動画で私見をアピールする専門家、風評を気にして手を引こうとする病院、医療関係者の子どもは保育園に来させないでと訴える保護者、感染してもいいから弟と一緒にいると譲らない兄、自分が船旅をしたいと言わなければ夫が感染することはなかった・・・と泣き崩れる妻、さまざまな人間模様を織り交ぜながら、約1ヵ月後に乗客乗員3711人全員が下船するまでを描く。

(C)2025「フロントライン」製作委員会
ぶつかりあうエゴ
立場が違えば、主張も違う。
だが私たちは相手の立場や状況を思いやることなく、自分の主張を押し通す。
その結果がなにに繋がるかなんてことは、考えもせずに。
感染対策の専門家だという教授が、YouTubeで船内対策の不備を糾弾した。
専門家の肩書きを盾に、対策のまずさを指摘し、自分が外されたことに対する不満をぶちまける。
マスコミはそれに飛びつき、センセーショナルに報道する。
現場のことを知らない国民は「なにやってんだ!」と非難する。
どれひとつとして、船内の状況を改善する役に立っていない。
自分も感染するリスクを負いながら職務についていた人たち、未知のウイルスに果敢に立ち向かっていた人たち、そこに行けない私たちの代わりに頑張ってくれていた人たちを、応援するどころか、さらにむち打つ結果に。
教授の憂さは多少晴れたかもしれないが、協力病院は次々と派遣スタッフを引き上げ、看護師の子どもは保育園に行けなくなり、結果、看護師も仕事に行けなくなり、医師の家族は差別に怯える。
最初9チームあったDMATも、2チームまで縮小せざるを得ない状況に追い込まれる、患者数はどんどん増えているというのに。
・・・専門家もマスコミも、なにがしたかったのか?
食い下がる取材陣に、結城が投げかけた言葉。
「あなたたち、どこか面白がってないですか?
本当にあの船に乗っている人たちの無事を祈って、報道してるんですか?」

(C)2025「フロントライン」製作委員会
藤田保健衛生大学の英断
船内での2週間に及ぶ隔離生活の後、陰性の乗客は下船を許可される。
だが陽性反応のある人と、陽性者の家族(濃厚接触者)は、さらなる隔離が必要だった。
どこに隔離するか?
手を挙げたのが愛知県の藤田医科大学岡崎医療センター。
関東圏に一件もなかったのか・・・と思わないでもないが、自衛隊の協力の下、100名以上がバスに分乗して愛知県に向かう。
途中、3名が車内で急変、近隣の病院に託すこともできず、そのまま愛知に向かうも、到着時には急変は7名に増えていた。
受け入れ先の医師・宮田(滝藤賢一)は、「軽傷者だけって話だった、約束が違う」と抗議するが、同乗してきた医師たちと対応にあたる。
実際に藤田大学は、オープン目前の医療センターを提供したのだが、映画で実名を出した点に、同業者は密かに拍手喝采した。
あれは本当に英断だったのだ。誰もが尻込みする中、大きなリスクを自ら引き受けてくれたのだから。
もし死者でも出れば、開業前に名前に傷がつくし、風評被害も出ただろう。
だが「私たちもなにかお役に立ちたいと思いましてね」と電話の向こうの関係者。(たぶん偉い人)
その男気に震える。
宮田が、横浜から患者に付き添ってきた真田に言う。
「君があの船で経験したことは、今後、必ずこの国の役に立つ。だから、僕にも教えてよ」
泣きっぱなし
泣く要素はあまりないのだけれど、それでも何度も涙がこみ上げて、ハンカチを手放せなかった。
私は最前線にいたわけではないけれど、医療の末端でコロナと対峙してきた。
ウイルスの正体が分からず、ワクチンも薬もなかった頃、ウイルスの毒性が強くて死亡率も高かった。
発熱患者が来院する度に、緊張が走った。
インフルエンザと同じ感染対策で、果たして大丈夫なのか、誰にも分からない。
院内を狂ったようにアルコールで消毒しまくったけれど、それで十分なのか、誰にも分からない。
感染するかもしれない怖れは、常につきまとう。
特に小さな子どもを持つスタッフは、もっと怖かったことと思う。
自分が感染して、もし子どもにうつったら・・・。
しかも医療現場なのに、マスクや消毒薬が不足して、私たちは使い捨てマスクをハイターで消毒して再利用していた。
クリアファイルを切り抜いてフェイスシールドを作り、100均の雨合羽を防護服の代りにした。
自分たちも困ってはいたけれど、日本中で品薄な備品は、実際のコロナ患者を受け入れている大病院に使ってもらいたいと、本気で思っていた。
ワクチンが出てきてからは、土日も返上し、夜は自治体の集団接種会場で働いた。
そこまで頑張っても、非難されたり、怒鳴られたりした。
苦しい日々だった。
そんなことが映画を観ながら次々思い出されてきて、涙がとまらなかったのだ。
ダイヤモンドプリンセス号で働いた医療関係者や自衛隊や厚生省や船のスタッフのご苦労とは比べものにもならないが、医療関係者でなくても、大人も子どももみんなステイホームを律儀に守り、頑張った日々があった。
ほんの2~3年前の話だけれど、もう忘れかけているね、私たち。

(C)2025「フロントライン」製作委員
Chikakoの感想
船に乗り込んで陣頭指揮を取る仙道医師の言葉が心に残る。
「こんな時に頑張らなくて、なんのために医者になったのよ。」
使命感・・・という言葉を、私たちは簡単に使う。
使命というのは、その人のミッション。この世に生まれてきた意味みたいなもの。
それは必ずしも経済活動に結びつくものではないかもしれない。
だがミッションを生きる人は、ただそうしたいのだ。
そうやって命を燃やしたいと願うのだ。
犠牲を払っても、損をしても、それでもやりたいことなのだ。
でもそれはその人のミッションであって、他人がただ乗りしていいものではない。
ミッションを生きる美しい人々が、妬まれたり、足を引っ張られたりすることなく、その仕事に邁進できるよう、応援する世の中を私たちは作っていきたい。

(C)2025「フロントライン」製作委員会