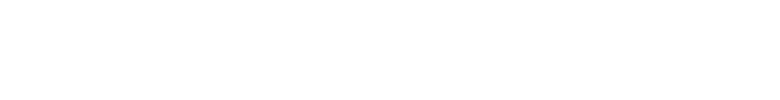大きな病院と開業医は役割が違う
大学病院をはじめとする基幹病院は、緊急性や専門性の高い医療を提供する施設です。 最先端の治療や手術ができ、入院設備を備え、術後のリハビリもできて、医師やナースだけでなく、たくさんのパラメディカルや事務スタッフによる、総合的な医療を受けられます。 一方、町の開業医は、それほど重症ではない患者さんを担当します。 扱う疾患や症状も、オールマイティではありません。 ですが、かかりつけ医として、風邪やインフルエンザや吐き下し、糖尿病や高血圧など持病のコントロール、足が痛い、腰が痛い、眠れない、不安がこみ上げる、めまいがする…からお嫁さんの愚痴まで、幅広く対応します。 また開業医には、患者さんの緊急性を見極める役割も求められます。 このまま経過観察をしてもいいのか、すぐに大病院に搬送するべきか、医師が適切な判断を下して、次へとつなげます。 たとえば身体が痺れるという訴えから、脳梗塞を疑って、設備のある大病院に送るのは、開業医の大切な役目です。 大きな病院と市井の医院は、そうやって医療の分業を目指しています。
それは高度医療を担う大学病院が、風邪やインフルエンザや小さな怪我の治療で忙殺されたら、困るからです。
最新鋭の医療機器を備え、最先端の医療を追求している大学病院や大きな病院は、クリニックとは違う役割を担っています。
そのため軽症患者さんが殺到しないよう、医院からの紹介状がなければ初診料が5000円かかるシステムが生まれました。
これは3時間待って3分しか診てもらえなかった…という患者さん側の不満解消にも繋がります。
大きな病院と市井の医院は、そうやって医療の分業を目指しています。
それは高度医療を担う大学病院が、風邪やインフルエンザや小さな怪我の治療で忙殺されたら、困るからです。
最新鋭の医療機器を備え、最先端の医療を追求している大学病院や大きな病院は、クリニックとは違う役割を担っています。
そのため軽症患者さんが殺到しないよう、医院からの紹介状がなければ初診料が5000円かかるシステムが生まれました。
これは3時間待って3分しか診てもらえなかった…という患者さん側の不満解消にも繋がります。
大きな病院を受診することになった
先日、職場の健康診断で血液検査を受けた際、ある数値が基準値の2倍、検出されました。 腫瘍マーカーという、放置できないカテゴリーだったので、大きな病院で詳しく調べることに。 受診したのは消化器内科。 担当してくれた医師は、紹介状と検査データを見比べて、腫瘍マーカーの数値が意味する可能性について説明してくれました。 膵胆管の腫瘍…、でも婦人科系や大腸も除外できないとのこと。 まずもう一度血液検査、そして内視鏡をしましょうか…と先生。 いや、いやいやいや、先生、内視鏡は4カ月前にかかりつけ医でやってるし、大丈夫!と全力で抵抗しました。 だってカメラ飲むの苦手…。(←子どもか!) ⇒3年ぶりに胃カメラ検査を受けてみた 先生は苦笑しながら、ではCT検査を…と言う。
CTとは、体の断面を輪切りにした画像を何枚も撮って、臓器の異常を調べる検査。
今回は血管に造影剤を入れて撮影する手の込んだやつです。
まあ、それなら点滴みたいなものだから、耐えられます。
「2時半に検査の予約を入れるから、いったん帰って、また来てね。あ、それまでは絶食で。」
…先生、私は昨夜の7時から、ずっと絶食なんですが、もっとですか?
お腹空いた…。
先生は苦笑しながら、ではCT検査を…と言う。
CTとは、体の断面を輪切りにした画像を何枚も撮って、臓器の異常を調べる検査。
今回は血管に造影剤を入れて撮影する手の込んだやつです。
まあ、それなら点滴みたいなものだから、耐えられます。
「2時半に検査の予約を入れるから、いったん帰って、また来てね。あ、それまでは絶食で。」
…先生、私は昨夜の7時から、ずっと絶食なんですが、もっとですか?
お腹空いた…。
CT検査を受ける
腫瘍…つまり癌があるかもしれないと思うと落ち着かないので、いったん職場に戻りました。 働いているほうが、気がまぎれるし。 ほどなくして先ほどの先生から電話がかかってきました。 「血液検査の結果が出ました。腫瘍マーカーの数値が半分になって、基準値内に収まっています。」 「え?それはどういう…?」 「理由はわかりません。3日で数値がこれほど変わるのは珍しいのですが、午後の検査をどうしますか?」 かかりつけ医とも相談して、異常値が出たことは事実なので、一応検査をしてもらうことにしました。 ですが、造影剤は使わず撮影だけする、ライトな検査に変更です。 画像撮影は、ものの10分ほどでした。
痛くもかゆくもなく、私はただ横になって、息を吸って~~止めて~~の指示に従うだけ。
時間がかかるのは、その後の読影と診断です。
閑散とした午後の待合室で、1時間くらい待ちました…、空腹のままで。(^^ゞ
画像撮影は、ものの10分ほどでした。
痛くもかゆくもなく、私はただ横になって、息を吸って~~止めて~~の指示に従うだけ。
時間がかかるのは、その後の読影と診断です。
閑散とした午後の待合室で、1時間くらい待ちました…、空腹のままで。(^^ゞ
検査結果は異状なし
先生が検査結果を手に、待合室まで来てくれました。「なにも異状は見つかりません。治療の必要なしです。」
これからしばらく、かかりつけ医で定期的に血液検査をして、経過観察をすることになりました。
CTを使った大掛かりな検査となりましたが、「異常なし」の一言でどれだけ安心することか。
検査は悪いものを見つけるだけでなく、悪いものがないことを証明するためにもあるんだなぁ…と思いました。
紹介状を渡された患者さんの気持ちが少し分かった
普段私は、町の小さなクリニックで働いています。
紹介状を準備するお手伝いもしますが、紹介状を渡されて大きな病院を受診する患者さんが、どんな気持ちになるのかが、少し理解できました。
なにも診断が下っていないうちに、あれこれ考えるのは無駄だ…と重々承知していながら、やっぱり考えてしまうものです。
もし残り時間が少ないのであれば、まず何をしたらいいんだろう…。
やり残したこと、言い残したことは、ないだろか?
今のうちに会っておくべき人は誰だろうか…なんて。
でも 紹介状 = 深刻なケース ばかりではありません。
私のように、検査で何もないことを証明するケースもあるのだから。
自分が不安を感じた分、患者さんの不安にも心を寄せていけたらいいな…と思います。